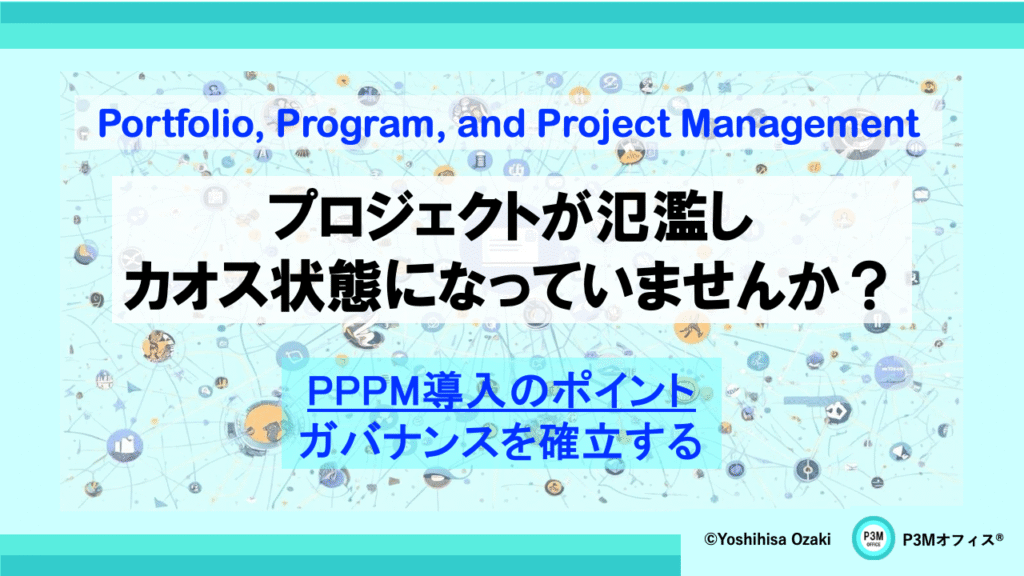〜 PPPM導入のポイント:ガバナンスを確立する 〜
目次
はじめに(近年、プロジェクトが増加の一途)
近年、企業・組織において、外部環境や内部環境で様々な変化が多く発生しています。外部環境では、国際紛争やアメリカの関税、今は少し落ちつていいますが感染症の問題、高齢化社会の加速、人口減少など、内部環境では、DXへの対応、働き方改革、業績悪化に伴うリストラクチャリングなど、企業・組織の状況によりますが、これらの変化はビジネスに大きな影響を与えています。
これらの変化に対応すべく、企業・組織ではビジネスを継続的に維持、発展させていくために、経営戦略・経営計画を立て、様々な施策、つまり多くのプロジェクトを立ち上げている状況です。また、現場では既存のオペレーションの効率化や生産性向上を実現するために、細かな改善活動やより良い方向に変えていくためのプロジェクトも多々実行している状況だと思います。皆さんが所属されている企業や、コンサルの方であれば支援先の企業ではどのような状況でしょうか。
プロジェクトが氾濫しカオス状態になっていませんか?
私は、様々な業種のプロジェクトマネジャー、プロジェクト関係者、PMO、コンサルの方々との交流がありますが、次のようなことを良く耳にします。
- プロジェクトや施策を開始する際の明確な基準がなく、誰か(上)の一声で決まる
- 部門内で多くのプロジェクトが立ち上げっているが、誰が何を担当しているかわからない
- プロジェクト全体を把握する部署・人が不明確、またそのプロセス・ツールが確立されていない
- 実施している全てのプロジェクトの進捗状況、課題、成果(もたらす価値)などを管理できていない
- 通常のオペレーションに加え、プロジェクトや施策が多く、人材不足に陥っている
言い方は良く無いかもしれませんが、まさにカオス状態にあると言っても過言ではないような状況でしょうか。まとめると、次の表のような状況に陥っているのではないでしょうか。
| 状況 | もたらす影響 | 結果 |
| プロジェクトの優先順位・選定などの基準が不明確 プロジェクト開始の判断プロセスが曖昧(誰が何を持って判断するか) 新たなプロジェクトが追加され、そのことを知らされていない プロジェクトの開始・中止の判断プロセスが無い | プロジェクトの数が非常に多い状況となる プロジェクトの多くが企業組織の価値、ベネフィットを創出しているかが曖昧となる 不要、無駄なプロジェクトが存在する状況となる 人材、工数不足に直面する | プロジェクトの結果(成果、価値)が経営戦略と整合しておらず、経営に貢献しない状況となる 本来優先される製品、ソリューションの市場への投入が遅れる プロジェクトが失敗する確率が高くなる |
これらが、幾つか当てはまるようであれば、何か手を打つ必要があるのは言うまでもありません。プロジェクト開始や中止の判断について、まずはしっかりとしたガバナンスを確立することが先決だと思います。そこでヒントになるのが、PMI(Project Management Institute)の3つのグローバル標準です。
- The Standard for Project Management, Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 7th (8th ) Edition
- The Standard for Program Management 5th Edition
- The Standard for Portfolio Management 4th Edition
プロジェクトの開始(中止)についてのガバナンスを考える
PMIの3つのグローバル標準ですが、総称してPPPM(Portfolio, Program, and Project Management)と呼んでいますが、この3つの標準で一貫しているのは戦略整合と価値へのフォーカスです。つまり営利団体の企業・組織で言いますと、経営戦略や経営計画と整合したプロジェクトを見極めて実行し、そのプロジェクトが経営に貢献する価値を創出するということになります。
この戦略整合と価値創出の観点でガバナンスをしっかりと確立することが、極めて重要になり、しっかりとしたガバナンスを確立すれば、前述のようなカオス状態に陥ることはありません。
では、どのようなガバナンスを具体的に確立すれば良いかをみていきましょう。戦略整合と価値へのフォーカスを考慮した上での、ガバナンスの3つの例(プロジェクトの選定・優先順位づけ、プロジェクトの承認、プロジェクト中止の判断)をご紹介します。
① プロジェクトの選定・優先順位づけ
限られたリソースを最大限に活用し、企業の戦略目標を達成するためには、プロジェクトの優先順位付けを実施し、正しいプロジェクトを選定して実行することが不可欠です。どのプロジェクトを開始し実行して、経営に貢献できるかを明確にして、その承認を得るガバナンスを確立することが重要です。その例を下表に示します。
| プロジェクト・ポートフォリオ計画の作成 | 何をもとに判断するか(判断基準など) | 承認する (承認者) | ポイント となること |
| PMO(EPMO) 経営企画部署などが 作成する | プロジェクトのビジネス価値、実現性、ビジネスドライバーなど | ステアリングコミティ、経営会議など(経営層、部門長などで構成) | 限られた経営資源で、どのプロジェクトをどのくらいの期間で実施するかをコミットすること 部門にまたがるプロジェクトは、特にステコミメンバーと確実に握ること |
欧米の企業においては、この優先順位づけを実施し経営層の承認をもらう役割は、PMO(どちらかというと経営層に近いエンタープライズPMOや、ポートフォリオマネジメントオフィス)が実施していることが多いと認識しています。
日本企業においては、このような部署や役割が明確ではないと思いますが、複数の部門を俯瞰してマネジメントする経営に近いところに位置付けられる役割になりますので、経営企画などが当てはまる部署かもしれません。
企業・組織の状況によって異なりますが、プロジェクトの優先順位付けを行うための主な判断基準の例をご紹介します。
プロジェクトの優先順位づけの主な要素
プロジェクトの優先順位付けを行う際に、考慮する主な要素は以下のとおりです。
- ビジネス価値: 企業の戦略目標に合致する価値を生み出すプロジェクトを選定します。これは、収益性、市場シェアの拡大、顧客満足度の向上など、様々な形で測定されます。
- 実現可能性: プロジェクトの複雑さ、リスク、利用可能なリソースなどを評価します。実現可能性が低いプロジェクトは、成功の可能性も低く、優先順位を下げることがあります。
- スケジュール(時間): プロジェクトの完了までの期間を考慮します。短期的、中期的、長期的な視点から、企業のニーズに最も合致するプロジェクトを選定します。
- ビジネスドライバー: 法的要件、システムのサポート終了など、実行が必須な要素を考慮します。これらの要素は、企業の存続に関わる可能性があり、高い優先順位が与えられます。
これらの要素でプロジェクトを比較した際のイメージです。(実際にはビジネスの価値、実現可能性などを可能な限り定量的に把握して比較します)
| プロジェクト | ビジネス価値 | 実現可能性 | スケジュール | ビジネス ドライバー | 優先順位 |
| 新規顧客獲得 プロジェクト | 新規顧客獲得による売上◯%増加、市場シェア◯%拡大 | 比較的容易、リスクは低い、必要なリソースの確保は可能 | 短期 (1年間) | なし | 高 |
| 新規製品開発 プロジェクト | 新規市場参入、既存顧客へのクロスセル、ブランドイメージ向上で売上◯%向上 | 複雑、リスクは高い、多くのリソースが必要 | 中長期 (3年間) | なし | 中 |
| 既設業務ITシステム更新プロジェクト | システムの運用コスト削減、セキュリティリスク軽減、業務効率向上 | 複雑、多大なリソースが必要、リスクは高い(広範囲の業務に影響) | 中長期 (2年間) | システムサポート終了 (EOSが3年後) | 最優先 |
| 法規制対応、コンプライアンスプロジェクト | 法規制遵守、罰金回避、企業のレピュテーション保護 | 比較的容易、リスクは低い、専門家のサポートを要す | 短期 (1年以内) | 法規制遵守 | 最優先 |
② プロジェクトの承認(Project Justification)
開始しようとするプロジェクトの目的、ビジネスケース(重要)、リスク、スケジュール、予算、もたらすベネフィット・価値などを、プロジェクト憲章に記載し、プロジェクトスポンサー(経営層など)の承認を得るプロセスは必須です。
判断する際に最も重要となるのが、プロジェクトの正当性(Justification)です。ビジネスニーズ、戦略との整合、期待するベネフィット・価値、投資対効果などを明確にし、プロジェクトマネジャーは達成することをスポンサーと握って、プロジェクトを開始させることが必須です。
| プロジェクト憲章 作成 | 何をもとに判断するか(判断基準など) | 承認 (承認者) | ポイント となること |
| プロジェクト マネジャー | プロジェクトの正当性、ビジネスケースなどを必ず確認し判断する | プロジェクト スポンサー (経営層など) | プロジェクトを実行する側と、経営側が共通の認識を持ち握る (コミットする) |
③ プロジェクト中止の判断
プロジェクトの承認を得て、プロジェクトをスタートさせたとしても、必ずしも計画通りのベネフィットや価値を得られるわけではありません。冒頭に述べましたが、外部環境や内部環境は日々変化しています。スタート時点で戦略に合致したプロジェクトを選定したとしても、戦略自体が変わってしまい、そのままプロジェクトを継続しても、経営に寄与する価値が得られないことが明確になれば、途中でプロジェクトの方向転換を実施することや中止する判断を実施しなければなりません。何もせずに継続することは、リソースの無駄に直結します。プロジェクトの中止を判断するガバナンスプロセスを確立することが必要となります。
| プロジェクト中止を 提言 | 何をもとに判断するか(判断基準など) | 承認 (承認者) | ポイント となること |
| PMO(EPMO) 経営企画部署など | 当初の計画とのギャップ、プロジェクトの進捗、ベネフィット・価値の予測、中止した場合の影響、リソースの状況など | ステアリングコミティ、経営会議など(経営層、部門長などで構成) | 戦略整合の再確認、 中止した場合の影響確認、リソースの再配分などスムースな移行を検討・確認 |
まとめ(最後に)
今後、これまで以上にプロジェクトは増加の一途をたどると予想しています。これまでの旧態依然の組織構造(オペレーションを中心とした階層的な縦割り組織)だけで乗り切れる時代は終わっていると率直に思います。今後、プロジェクトを主とした考え方・組織などを取り入れていくことが求められます。今回ご紹介したガバナンス構築はほんの一例です。
また、経営層こそがこのようなことを理解してリードする必要があると言う声もよく聞きます。そのとおりだと思います。ただプロジェクトマネジャー側でも、プロジェクトが達成する価値を明確にして経営層と握ることも極めて重要です。プロジェクトマネジャーはこれまでQCDを達成するための戦術に磨きをかけてきましたが、今後はそれに加えて、戦略レベルの知識やノウハウ(ファイナンス知識を含む)に磨きをかけることが必要だと思います。欧米では、戦略的プロジェクトマネジャーという上記の役割が出現しています。
また、世界各国では、プロジェクト・ポートフォリオマネジメントを取り入れてEPMOを組織化し、ご紹介したガバナンスを構築している企業が多いと認識しています。PMI PMO Global Awards 2025にノミネートがあった世界各国の優れたPMO組織は、今回ご紹介したようなガバナンスをしっかりと構築しています。
以上、長くなりましたが、少しでも皆さんのご参考にしていただけることがあれば幸いです。お読みいただきありがとうございました。
追伸:ご紹介したプロジェクトの優先順位づけや組織の考え方などは、拙著「プロジェクト・ポートフォリオマネジメントの教科書」で解説しておりますので、ご参考にしてください。
また、プロジェクト・ポートフォリオマネジメントを実践レベルで学べるワークショップにも講師として登壇しております。直近では、2025年11月7日にPMI日本支部主催 スキルアップ研修「ポートフォリオマネジメント実践ワークショップ」が開催されます。ご興味のある方は是非ご参加ください。